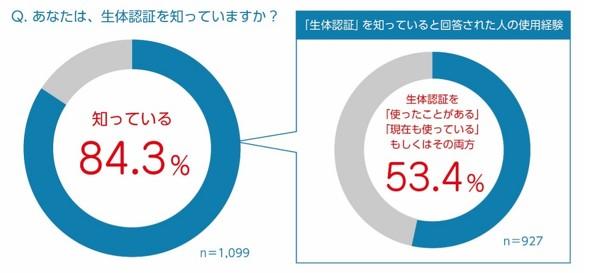本稿はKDDIが運営するサイト「MUGENLABO Magazine」に掲載された記事からの転載
ここ10年の企業のオープンイノベーションや協業・共創環境を語る時、特徴的なポジションとして「専業プレーヤー」の存在が挙げられます。戦略コンサルティング・ファームやベンチャーキャピタルによる支援先の売却支援のような個別企業の取り組みを支援するものではなく、より幅広いプラットフォーム的な役割を担うものです。
大きくは協業・出資先を探し出すソーシングの機能を持ったデータベースと、より事業そのものにフォーカスしたハンズオンのものに分かれます。前者にはCrunchBaseやAngelListがあり、後者にはTechStarsや Y Combinatorなどが立ち上げたアクセラレーション方式がありました。特に後者はファンドでもありながら、その後のラウンドで企業との結びつきをより強くイメージした企業協賛型のプログラムが生まれており、これが日本国内でも数多く取り組まれたのはご存知の通りです。一方で主導する企業側には高度なスタートアップ投資への知識・理解、そしてなにより社内での体制が必要となり、各社が本格的に取り組みを本格化させるには数年の時間が必要でした。
このように、日本国内で新しい形でのオープンイノベーションへの取り組みが始まって10年が経過します。各社の取り組み姿勢や状況はどのように変化したのでしょうか?本稿では国内でいち早く、このオープンイノベーションに関わる専業プレーヤーとして独自の取り組みを続けた4社に集まっていただき、国内における共創の現在地について語っていただきました。(文中太字の質問は全てMUGENLABO Magazine編集部、回答は以下の方々・敬称略)
座談会参加者eiicon company代表・founder/中村亜由子さん01Booster(ゼロワンブースター)代表取締役CEO/鈴木規文さんCreww代表取締役CEO/伊地知天さんKDDI ∞ Labo(KDDI)/石井亮平さん
オープンイノベーション、企業協業を支援する立場で取り組んできた4社のみなさんに集まっていただきましたが、まず、この5年から10年の市場環境の変化について聞きたいと思います。KDDI ∞ Laboは2011年開始なので中でも最も古いプレーヤーになりました
石井:そうですね、KDDI ∞ Laboは今年でちょうど10年を迎えますが、開始当時はフィーチャーフォンからスマートフォンに代わるタイミングでした。いわゆる『ガラケービジネス』が崩れていくという中で、スマホのビジネスをどう作るのかという明確な課題があったんです。通信キャリアもアプリで差別化が必要と考え、新しいスタートアップと一緒に協業するのがよいだろうというのが出発点でした。ただ、これが2010年代半ばになると、アプリビジネスにおいて勝敗がはっきりしてきて、スタートアップがリアルとかIoTに主戦場を移し始めてきたんですね。
KDDIはウェブ上だけであれば送客などで力を発揮できたかもしれませんが、ビジネスが「リアル」になってくると勝手が変わってきます。そこでリアルなアセットを持つ大企業の力を借りてみんなでスタートアップとの協業・共創に挑戦しようと発展したのが、現在も続くパートナー連合の考え方です。ただ、まだまだ自主的にこういった共創活動を推進しようというのはごく一部の企業に留まっている印象はありますね。
Crewwは2012年から開始していますが傾向に変化はありますか
伊地知:2012年にオープンイノベーションプログラムの提供を開始をしてから首都圏では多数のプログラムが開催されていましたが、首都圏以外での取り組みは限定されていました。ここ数年、地方の中堅企業とスタートアップの共創がCrewwのプラットフォーム上で多数開催されるようになりましたね。総じてシード期のスタートアップと地方の中堅企業との相性は非常に良いと感じています。例えば、プロダクトがある程度検証できていてあとは拡販だという時は、スタートアップは大手企業と組むことをイメージしやすいと思います。一方で、プロトタイプを検証していくフェーズではそれほど大きな顧客基盤が必要ではありません。むしろ規模より検証までのスピードをあげることの方がプライオリティが高いケースがよくあります。
なるほど地方の中小企業にも協業や共創の考え方が広がりつつあると。AUBAは2017年から開始していますが同じような状況でしょうか
中村:私たちはあらゆる企業のオープンイノベーション実践をフツウゴト化するため、2017年に立ち上がったのですが地方の中小企業さんなどは当初、無料でも使ってもらえなかったりしましたね。オープンイノベーションって首都圏の話でしょ?という感覚はあったと思います。
ただそれが徐々に変化してきて、19年に前政権下で各自治体がイノベーション予算を使えるようになり、地域に企業を誘致・支援する機運が高まったのがひとつのきっかけになったと思います。最初はスタートアップに会える、会えないという課題感でしたが、現在は協業した上で社会実装をどうするかとか、事業化をどのようにすればよいか、といったフェーズに移っています。

伊地知:地方の中堅企業ですとオーナー社長の場合も多く、フットワークが軽いのでスピーディーに協業や検証に進むことができます。スタートアップもフェーズによって組むべき相手が本来違うはずなので、「地方中堅企業xスタートアップ」というのは本質的にWin-Winになりやすいモデルなんです。地方には技術に優れている企業も沢山いらっしゃるので技術とのコラボレーション事例というのも今後どんどん増えていくと思います。また、日本企業と海外スタートアップのようなクロスボーダーの取り組みも今後はニーズとして高まっていくと思いますので、ぜひこういった仕掛けもしていきたいですね。
具体的な事例にはどういったものがありますか
中村:例えば宮崎県の近海かつお漁業を生業とする浅野水産と大手町のAIスタートアップFACTORIUM(ファクトリアム)の事例では、漁労長の勘をAI化するという「ベテランのAI化」を目指し、水産業の高齢化に対する解決策を共創により模索されるケースがありますね。
現在は様々なセクターのデジタル化が叫ばれるようになりましたが、特に地方創生、一次産業のデジタル化やAIの活用はまだ社会実装が進んでいない状況です。一方これまでは都心部に数の多いスタートアップと地方の事業者が繋がることはほぼなかったのですが、プラットフォームができたことでAUBAの利用が進んでいる状況です。
ゼロワンブースターさんも2012年開始で多数の共創プログラムを手がけられたと思いますが、企業のオープンイノベーションに対する考え方はどのように変わったと感じられてますか
鈴木:オープンイノベーションのブームがピークを越え、結果の不透明さが浮き彫りになったことにより、社内コンセンサスを得る難易度が増しましたね。コロナ禍において、イノベーションの必要性は高まっていますが、不透明な結果に対して合理的な意思決定がしにくくなるため追加投資を慎重になっているケースが増えている印象です。
ただ、中長期的にはイノベーション活動が活発な企業の方が収益性が高いというのが統計上出ているわけで、ここに短期業績主義のジレンマがあります。ゆえにプラットフォーマーは、時間軸と企業単位の壁を超え、データや事例を示し続け、意思決定のサポートをしなければなりません。また、イノベーション活動は大抵、組織ではなく「特定の個人」の思いによりドライブされています。その「個」を援護するのも我々の役割で、弊社「イノベーション担当者コミュニティ」はご担当者を支える大変意義深い場になっています。
新規事業というのは失敗の連続、特に非連続な成長を求めるパターンでは、慣れないことも多く、必然的に成功確率は下がると思います。スタートアップや他の企業との協業・共創でミスが発生するケースはどういうものがありましたか
中村:契約を結ぶ前に進むケースは危険ですね。法的な拘束力を持たない進め方、特に口約束でNDAも結ばないまま進行させる中小のケースは度々目にしました。NDAの中にNDAとは関係のない内容が入っていて、締結した後に知財をロックされた、なんていう事例もあります。特許庁がオープンイノベーションに関するガイドラインを作っているのでそういうものを参考にするとミスは減ると思います。
鈴木:そうですね、オープンイノベーションは相互の活動ですし、大手企業にも、スタートアップにも文化があります。どちらか片方の当事者のお行儀を責めてはなりません。大手企業の方が傾向的に変化への対応が鈍いのも事実です。下請けを選ぶことに慣れている会社はどうしてもスタートアップを下請け扱いし、イコールパートナーシップが成り立たないケースはありました。
大手企業の人事異動もスタートアップにとっての組みづらさに繋がります。熱量のある大手企業側の担当者が異動してしまえば、揺り戻しがきて、スタートアップへの協力姿勢は低下します。それだけであればいいのですが、大抵前任者否定的な体制になることが多いため、施策の連続性が保てないのです。そのためには、社内全体の文化や風土をオープンイノベーションマインドに変える必要があり、相当の時間がかかってでも取り組まざるを得なくなっていると思います。
伊地知:10年近くこの分野で多くの企業と一緒にやってきた結果、上手くいくパターンと上手くいかないパターンが見えてきました。上手くいっている企業はオープンイノベーションのゴールを「継続的にイノベーションを生み出せる組織づくり」とし、その過程での新規事業創出の手法(ビジネスマッチング、CVC、アクセラレーター)はあくまでゴールに行き着くまでの途中経過であると考えている場合が多いです。もちろん各社全力でそれぞれの新規事業の創出に取り組むのですが、この一連の取り組み・経験を通じて、毎年自社のイノベーションのステージが上がっていっていることを定性的・定量的にKPIとして計っていますね。
新規事業における時間軸・視点の置き方は確かに難しいですよね
伊地知:上手くいかないパターンとしては、ビジネスマッチングやアクセラレーターを単発で実施して、どれくらいの規模のビジネスが生まれたかを評価にしている場合です。これですと、いきなり大きな売上を生むビジネスが生まれない限り、翌年の継続はなかなか難しくなります。仮に初回から大きなビジネスが生まれたとしても次回以降の再現性はありませんし、ノウハウを積み上げて人や組織を進化させていく中長期の活動がオープンイノベーションの本質的な価値をつくり上げていくと思います。
実際に全くスタートアップとの関わりがなかった建築・土木分野の企業でも、アクセラレータープログラムでスタートアップとの協業を経て、出資に至り次のイノベーション創出の取り組みを探されていたりします。また、金融系企業のケースですと、最初はベンチャーキャピタルへのLP出資から始まり、スタートアップとの協業、出資、専門部署の立ち上げ、海外企業の探索、海外企業との協業・出資など4年間ほどでかなりイノベーティブな取り組みを自走されるようになっています。企業がオープンイノベーションをどのように評価するかというKPIの設定を間違えると継続性がなくなり、その設定を上手くやれば年々イノベーティブな組織になっていくという現象を何度も目の当たりにしています。
後半につづく
BRIDGEでは会員制度「BRIDGE Members」を運営しています。会員向けコミュニティ「BRIDGE Tokyo」ではテックニュースやトレンド情報のまとめ、Discord、イベントなどを通じて、スタートアップと読者のみなさんが繋がる場所を提供いたします。登録は無料です。無料メンバー登録